本日の講義の流れ
▼廣瀬先生 ― (講義)意思決定のためのSPICEアプローチ
▼田村先生― (演習)SPICEアプローチの実践
4月29日(月)は、「対話力の5ステップ SPICEアプローチ」についての授業が行われました。
冒頭の自己紹介セッションに続き、朝日大学法学部講師であり本センター客員所員でもある廣瀬先生より、SPICEアプローチに基づく利害関係者の分析についてご講義いただきました。
具体的な事例を交えたわかりやすいご説明により、対話力の重要性を改めて認識することができました。
後半の演習では、国際的な立場の違いを踏まえた模擬議論を通じて、合意形成のプロセスを体験しました。SPICEアプローチを実践的に活用しながら問題解決に取り組む力を養うことができた有意義な時間となりました。

履修生の学び 〜講義後に提出される振り返りシートより抜粋
●経済学部3年
最初のケースでは、立場が決められていたため、つい各立場の意見を求めたり、想像した者の中からその立場の意見を厳選してしまった。その結果、会議で出たステイクホルダーの数の方が自分が想定したものよりも少なくなってしまった。この点について、会議の中で互いに相手をライバルとして扱い、自らを有利に進めようと画策したことが原因であると感じた。仮に会議の結果自分に有利な結論が出せたとしても、考慮されていなかったステイクホルダーから異議がでた場合、会議そのものが意味を失い、全員が損をすること、及び創造的選択肢が限られてしまうことを考えると、今回のように拡散フェーズでライバル関係を意識することは不適切であると思った。拡散フェーズはとにかく意見を出し、収束フェーズでライバル関係を意識するといった形でフェーズごとに立ち回りを区別するべきだと考える。
二つ目のケースでは、選択肢を出すことは誰もが意識できたものの、「課題」と「創造的選択肢」が混在した結果、議論が右往左往してしまい、議論が収束へと進まなくなってしまった。ファシリテーター等が、各意見のSPICE上の位置付けを意識し、意見を出すタイミングをコントロールすることが求められると感じた。
●法学部法律学科4年
本日の講義では、対話を通じて問題を解決するための「SPICEの法則」に基づいた5つのステップ(状況把握・利害関係者、視点、課題設定、創造的選択肢、評価・意思決定)について学んだ。特に印象的だったのは、課題設定において相関関係と因果関係を正しく区別する重要性だ。データや現象を見た際に安易な結論に飛びつかず、背景や因果関係を丁寧に分析する視点は、実際の交渉や問題解決においても不可欠であると感じた。また、創造的選択肢を生み出すためのブレインストーミングや、意見の拡散と収束を意識するプロセスは、実践的な手法として今後のグループワーク等にも活かしたい。ボート部での経験を通じて、チームでの協力や意見交換の重要性を痛感してきたが、この講義で学んだ視点の多様性や意見の評価方法は、今後の交渉やチームワークにも大いに役立つと感じた。対話においては、単なる主張のぶつけ合いではなく、多様な視点と選択肢を受け入れ、論理的かつ柔軟に意思決定する姿勢の重要性を改めて実感した。
●法学部法律学科3年
SPICEの法則に基づく対話力向上の講義を受け、対話における論理的な構造化の重要性を改めて認識しました。SPICEを順に踏むことで、対話が単なる意見交換に留まらず、建設的な合意形成へとつながることを実感しました。
まず「状況把握・利害関係者」では、対話の前提となる現状や関係者の立場を整理することで、議論の土台が明確になります。続く「視点」では、関係者それぞれの価値観や考え方を理解し、発言のない利害関係者の意図まで読み取ることで、あらゆる意見を取り入れ、客観的に捉える視点獲得能力による共感や相互理解を深めることができます。
「課題設定」においては、因果と相関の違いに着目するなど、単なる不満や意見の羅列に終始せず、対話の目的や解決すべき課題を明確にすることの大切さを学びました。「創造的選択肢」では、既存の枠にとらわれず多様な解決策を出し合うことで、より良いアイデアや妥協点を見いだせる点が印象的でした。最後の「評価・意思決定」では、提案された選択肢を客観的に評価し、最適な解決策を合意形成するプロセスの重要性を理解しました。
このSPICEの5ステップを意識することで、感情的な対立や一方的な主張に陥ることなく、論理的かつ協調的な対話が可能になると感じました。今後の講義内の議論において、学んだフレームワークを実践に活かし、より良い人間関係や問題解決に貢献したいと考えます。
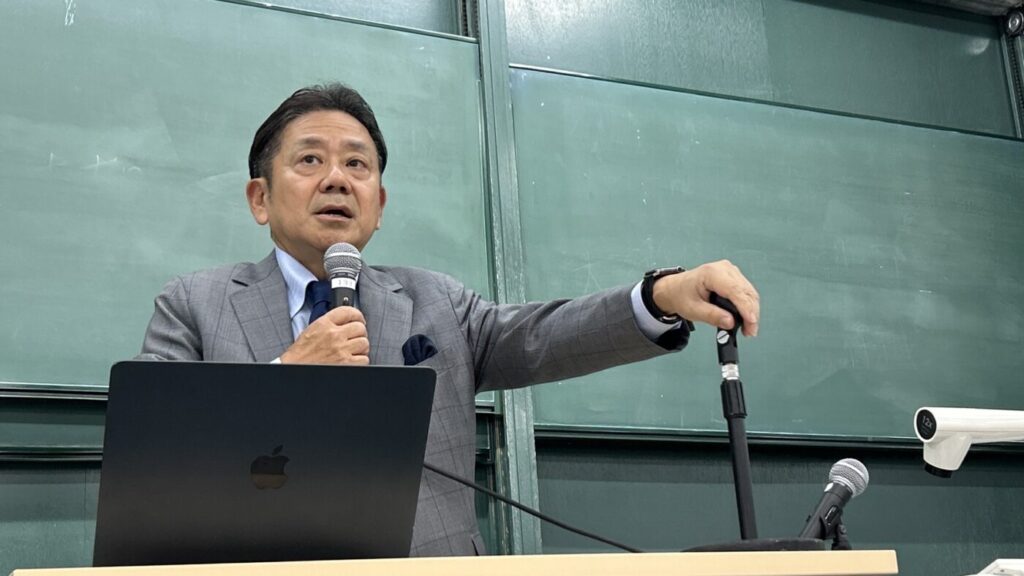

 Twitter
Twitter Instagram
Instagram
