本日の講義の流れ
▼田村先生→(講義)傾聴力について
▼社会人TA古山さん→(自己紹介・演習)SPICEアプローチ・アプリシエイションとアサーティブネスの実践
本日は、まず自己紹介セッションを通してお互いを知る時間を持ったあと、田村先生より「傾聴力」の中でも特に“AA”のポイント、そして問題解決において「選択肢を持つこと」の重要性について講義をいただきました。
また、社会人TAの古山さんからは、ケーススタディの意義や実務経験に基づいた気づきについてお話いただき、実践的な視点を学ぶ機会となりました。
ケーススタディでは、正当な業務行為と、社会的・経済的な価値観との間で衝突が生じる状況を取り上げ、グループごとに問題解決につながる選択肢を洗い出し、議論を深めました。
さらに、業務上正当とは言えない行為が従業員によってなされた事例についても検討。関係者それぞれの立場を想像しながら、問題の背景や対応策を考えることで、より深い傾聴力の理解へとつながりました。
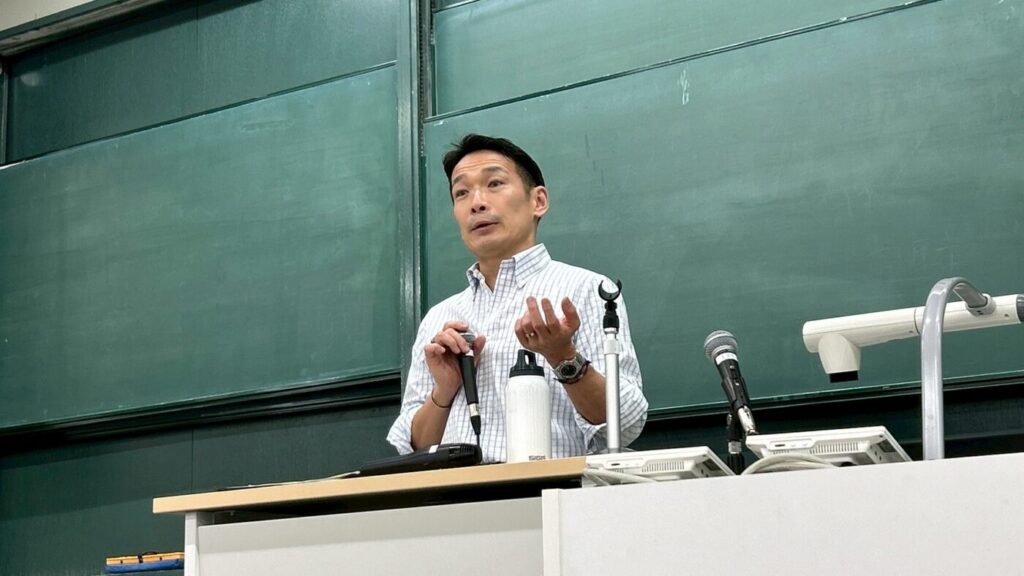
履修生の学び 〜講義後に提出される振り返りシートより抜粋
●法学部法律学科3年
今回の授業を通じて、自分がまだ十分に他者の視点を持ちきれていないことに気づかされた。特に、自分が関係者の立場になって考える場面では、どうしても目の前の問題や関係する直接的な相手ばかりに意識が向いてしまい、間接的に影響を受ける他の利害関係者にまで思いを巡らせることができていなかった。結果として、信頼回復や危機管理においても、広い視野を持ちきれず、対応策が限定的なものになってしまったと反省している。ただ、そのことに気づけたのは、他の受講者の意見を丁寧に聞く機会があったからであり、自分ひとりでは考えが及ばなかったことにも触れることができた。そうした対話や共有の場があることで、自分の視野がどれだけ限られていたか、また今後どのように広げていくべきかを実感する貴重な体験になった。リーダーシップを考えるうえで、自分の立場からだけでなく、あらゆる関係者の感情やニーズを想像する力が不可欠であると再認識した。今後はその意識を持ちながら、思考の幅を広げていきたい。
●法学部法律学科3年
今回の交渉学のケースを通じて、特に印象に残ったのは他者の意見を踏まえた上で自分の意見を述べることの重要性だ。バンクシーのケースにおいて、ある参加者が「この意見は新しい視点だった」と他の意見に言及しながら自分の主張を展開していたことで、議論が一段深まり、建設的に進んでいく様子を目の当たりにした。これまで学んできた「傾聴力」が、単なる受け身ではなく、議論を前進させる起点になることを再認識できた。
また、今回のケースを通じて、議論において利害関係者の視点を踏まえることの重要性を実感した。自分の意見だけでなく、関係する立場の人々の視点を整理したうえで発言することが、より建設的な議論や合意形成につながると感じた。また、ファシリテーターとして議論を進める際も、発言内容を要約するだけでなく、それぞれの意見がどの利害関係者を意識しているかに注目することで、議論の質をさらに高められると学んだ。
●商学部3年
今回の講義では、相手との信頼関係を築くための「傾聴」や「アサーティブネス」の重要性を学ぶことができた。特に自分の印象に残ったのは、「相手の立場を理解しつつ、自分の意見も尊重する」姿勢が、円滑な対話や交渉に不可欠であるという点だ。確かに、人と対話したり議論したりする際に、相手の意見を尊重する姿勢を見せないと、相手は自分の意見を聞く気持ちにならなくなってしまうと思った。自己紹介では、相手に関心を持って質問することで、自然な対話が生まれ、関係性の構築ができることを実感した。また、ビン・ラディン作戦における意思決定プロセスからは、複数の選択肢を持つことの重要性と、想定外を減らすための準備の大切さを学んだ。これらの学びは、交渉だけでなく、日常の人間関係にも応用できると感じた。今後も相手を理解し、自分も主張する姿勢を大切にしたいと思った。


 Twitter
Twitter Instagram
Instagram
