特別講義:サーラコーポレーション代表取締役兼CEO神野吾郎さん
〜神野さんのアイデンティティや取組みについて〜
本日(6月24日)は、サーラコーポレーション代表取締役兼CEOの神野吾郎さんにご登壇い
ただき、リーダーとして活躍される神野さんのアイデンティティや取組みについてお話い
ただきました。オーセンティックリーダーシップを発揮して社会で活動されている神野さ
んのお話を伺い、履修生各自が持つWILLを発展させる機会となりました。
次に田村先生と神野吾郎さんの対談を通して、慶應義塾大学の在り方や学生時代にやっ
ておくべきことについて考えました。履修生からの質疑応答では、就職活動の悩みや神野
さんの活動、組織としての動き方などについて質問が挙がり、履修生の将来の進路につい
て考える機会となりました。

履修生の学び 〜講義後に提出される振り返りシートより抜粋
●法学部法律学科4年
本日の講義では、サーラコーポレーション社長であり慶應義塾の評議員でもある神野吾郎氏から、リーダーシップや大学教育の在り方について学んだ。神野氏は、リーダーとは特別な資質を持つ人ではなく、多様な人と関わり、経験を積む中で育つ存在であると語る。学生時代はリーダー気質でなかった自身の経験を踏まえ、立場や環境によって人は変わり得ること、そして周囲から学び続ける姿勢の重要性を強調されていた。また、限られたリソースの中であっても前に進むこと、既存の仕組みを尊重しつつ新しい挑戦をトランスレートしていく柔軟性が求められるという点は、交渉学で学んだ「対話による合意形成」と深く通じるものがあった。
特に心に残ったのは、大学で学んだ者は、単に金を稼ぐためだけでなく、社会に対して何かを成し遂げる責任があるという視点である。私自身、来年から社会に出るにあたり、リーダーシップとは声を上げることではなく、耳を傾け、考え、行動することだと捉えている。今日の学びを胸に、私も社会に価値を残せる人間でありたい。
●法律学部法律学科3年
神野さんのお話を伺って、特に印象に残った点がいくつかあった。まず、多くの事業や企業にご自身で同時に関わっているという点である。私はこれまで、何事も一つに集中すべきであり、手を広げすぎるとどこかが疎かになるのではないかと考えていたため、そのような姿勢にはやや否定的な印象を抱いていた。しかし神野さんは、実際に多様な現場に身を置いてこそ得られる経験や知見があり、それが本業にも好影響を与えると語っていた。この考え方には大きな発見があり、自分の視野の狭さに気づかされた。また、手広く活動する際に大きな障害となる「時間」についても、「どうせ時間はないのだから、限られた中で自分が何をしたいのかを考えることが重要」という言葉が非常に印象的だった。これは企業運営に限らず、私たち学生の学びや将来のキャリア形成、日々の生活にまで通じる普遍的なメッセージであると感じた。忙しさを理由に挑戦を後回しにしていた自分にとって、挑戦の姿勢そのものを見直すきっかけとなった。
●法学部政治学科3年
交渉学の授業で神野吾郎社長のお話を伺い、大変感銘を受けた。特に印象的だったのは、神野社長がこれまでの会社の歩みの中で、いかに多様な視点を取り入れ、新たな価値を創造してきたかという点だ。
講義では、実際のビジネスにおける交渉の場面が、具体的なエピソードを交えて語られた。単なる「交渉術」というテクニック論ではなく、相手の立場や背景を深く理解し、そこからWIN-WINの関係を築き上げるための共感力と洞察力が重要だと感じた。神野社長の言葉からは、交渉とは単に自分の主張を通すことではなく、関わる人々との信頼関係を築き、より良い未来を共に創り出すプロセスなのだというメッセージが伝わってきた。複雑な状況下で、いかにして合意点を見出し、関係者全員が納得できる解決策を導き出すのか、その過程を神野社長ご自身の経験に基づいて学ぶことができたのは、非常に貴重な機会だと思う。今回の学びを、今後の様々な場面で活かしていきたいと感じた。
●法学部法律学科4年
サーラコーポレーション代表取締役社長であり慶應義塾評議員でもある神野吾郎氏をゲストに迎え、ご講義をいただいた。神野氏は、交渉を単なる利害調整の手段ではなく、「共創」のためのプロセスとして捉えるべきだと説いた。特に印象的だったのは、企業と地域社会、行政、大学など異なる立場の人々が対話を通じて信頼を築き、未来志向の価値をともに生み出していくべきだという視点である。また、交渉においては相手を説得するのではなく、共通の目的を共有することが出発点であると強調されていた。さらに、交渉は個人の力量ではなく、関係のデザインと場づくりが本質であるという考え方は、従来の「勝ち負け」の交渉観を大きく覆すものであった。今後、自分が何らかの交渉の場に立つ際には、こうした「共創型交渉」の姿勢を意識したい。
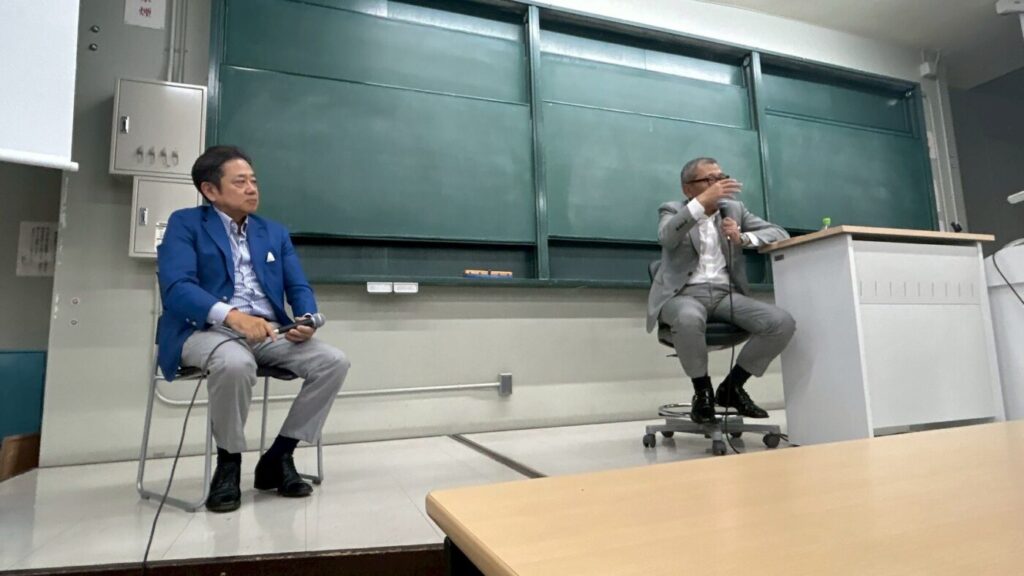
 Twitter
Twitter Instagram
Instagram
